はじめに:増え続ける不登校
文部科学省が公開している最新の資料によると,令和5年度において「不登校」と判断された児童生徒数は,小中高校生を合算して41万人を超えました1。特筆すべきは,このうち欠席日数が90日以上の子の割合が小中で5割を超過しており,この傾向が5年連続続いていることです2。
高校生の「1,000人当たりの不登校生徒数」も,コロナ禍が発生した令和2年以降増え続けています(R5: 23.5%)3。
不登校は増加+欠席日数の長期化など実態も深刻化している。
実は現在教員として働いている私も,小・中・高とそれぞれでかなり大きな不登校を経験しました。この記事では,そんな私の実体験をお話しし,「元・不登校当事者」の教員として思うことをお伝えしていきます。
今まさに「学校に行きたくない…」「生きるのがしんどい」という思いを抱えながら過ごしている人へ,一番に届くことを願います。
小学生―苦痛で仕方なかったクラスの騒音―
いじめまではいかなかったのですが,ハーフという周囲とは明らかに違う特質で身長も周りより不自然に高かったので,奇異や揶揄いの言葉を毎日投げかけられました。元々遊び相手は男の子たちの方が多かったものの,同じくらいの割合で揶揄ってくる子たちもいて,わざと追いかけ回されたり,ドッヂボールでも標的にされるのは当たり前。
特に授業中の男子たちの奇声を聞くのが苦痛で,担任の先生が叱らないように(=負担が増えないように),私から注意するとまたそれでいじられるというサイクルでした。今も男の子が金切り声を発したり,大人の男性がノリノリで騒いだりしているような環境は苦手です。
両親ともに持病をそれぞれ抱えていて不安定だったので,私が守らなきゃという無意識の作用もあったのかもしれません。
そんなこんなで小4のある日を境に,突然学校へ通いづらくなりました。幸い,母も父も私の過敏さに理解があったので,登校できなくなったことを責めることなく,私のしたいように過ごさせてくれていたのが救いでした(このスタンスは中・高通して変わりませんでした)。
ただ小5に上がる前には、これも唐突に行けるようになったんですね,不思議なことに。相変わらず何か言ってくる子たちもちらほらいましたが,不登校前よりも仲間として認めてくれている空気がありました。

前まで陰口をきいていた女の子たちと普通に打ち解け合い,バドミントンの部活もエンジョイしていました。腕のほどはへっぽこでした( ´艸`)
こうして苦難もありつつ,後半には友達にも恵まれ,そのまま中学校に上がってさらに青春を謳歌する…とは都合良くいかないのが人生。むしろここからまた一段とハードモードに突入することになります。そう,引っ越しに伴い,私を取り巻く環境が天変地異レベルでがらりと変化したのです。
中学生―違いすぎた他県の文化,拒食症へ―
中学に上がる年に他県へ引っ越し,小学校後半で築き上げた友達との輪からは完全に外れてしまうことになります。ハーフの子が多い地域の学校でしたので,小学校の頃のようにクラスで浮いたり何かにつけていじられることはありませんでした。同じ塾に通う友達も数人でき,同級生との会話は楽しい記憶が大半を占めています。
いわゆる地域では進学校の部類に入っていたので,席次をめぐって成績争い(それでもじゃれ合い程度でしたが)が頻発。もともと勉強は好きだったので,「勉強で負けたくない!」という思いはたしかに強かったと思います。中2から入部した合唱部の練習も充実感とともに取り組んでいました。
一方,いかに進学校であろうとも,そこは中1。授業を引っかき回そうと躍起に走る男子たちも当然いました。特に数学・理科の先生は一度怒鳴ると自ら授業をボイコットするタイプの先生だったので,「何とか怒らせないよう私が注意して見張っておかなきゃ…」と,なぜか私が一人で気を張り続けていました。ただでさえ授業中の奇声に悩まされていたのに,二重にストレスでした。
良い席次をキープするための勉強に,授業中の「見張り」,謎の孤独感…と,次第に雲行きが怪しくなり,「どんなに頑張っても,どうせいつか死んだら全部消えちゃうのに意味があるのかな」とまで思いつめていました。少し気分が上向きになっても,ふと黒い力に押さえつけられて絶望感が胸を覆うという繰り返しでした。
中2の終わり頃,ついに自暴自棄的に食べなくなり,わざと体重を減らし楽しんでいました。拒食気味になった挙句,栄養失調と肺炎で入院し,勉強に打ち込む云々どころの話ではなくなったため,中3で母の実家近くの中学校に転校。郊外の落ち着いた学校で,同級生も理解を示してくれたおかげで拒食症は回復しました。
この時期の絶望感・虚無感を当時の私に説明しろと言ってみたところで無理でしたし,両親にも心配をかけまいと繕っていたことも否定できません。
高校生―暗黒だった高2の記憶―
できれば騒音に悩まされにくい,勉強に集中できる高校にしたいと思い,県内の理数系の高校(当時SSH指定校)に進学。幸い周りには勉強熱心な子たちや(良い意味で!)オタク気質の子たちが多かったので,割とすぐに友達もできました。
高1の夏,当時の英語の先生が演劇部顧問も兼任されていて日頃からよく話もしていたので,いつの間にか演劇部に入ることになりました。校内のスピーチコンテストで皆から「感動した」と言ってもらえたり,演劇部の活動にも慣れていったりと,滑り出しは順調でした。
た~だですね…問題はここからです。
月日が経つにつれ,顧問の先生に,生徒として以上の要求をされるようになっていきました。当時はその時の困惑を言語化することもできませんでしたし,ましてやそれを学校の友人たちに相談することもままならず,どんどんその先生との関係性が歪なものになりました。
いわゆる「感情労働」の側面が強まりすぎたのだと思います。勉強や友だちとの関係づくりを楽しむべき時期と,ちょうど重複してしまった感じですね。今でも高1の時の心境を思い出すと「うっ…」と胸が詰まるので。
勉強面(特に恐るべき数学‼)での大変さも相まっていたと思いますが,高1の一連の出来事がトリガーとなって,精神崩壊手前まで追い込まれることになります。この頃から自分で意図的に髪の毛を抜いてしまう,いわゆる抜毛症(トリコチロマニア)が顕著になりました。
抜毛症とは?
DSM-5では強迫神経症の一種として指定。「抜毛症の患者は,美容以外の理由で毛髪を繰り返し引っ張ったり,引き抜いたりする。最も多いのは頭皮,眉,および/または眼瞼からの抜毛であるが,あらゆる部位の体毛が対象となりうる。(中略)抜毛症の成人患者の約80~90%が女性である。」4
本格的に学校へ行けなくなったのは高2の半ばからでした。朝,校舎を見る度に震え,「ここに閉じ込められたまま帰れないんじゃないか」と泣きじゃくっていました。休み時間ごとに教室を抜け出しては外廊下の隅っこで母に電話したり(当時はガラケー),iTunesで音楽を聴いて心を落ち着かせたり…と,ひたすら不安感と闘っていたことを鮮明に覚えています。「真面目に必死で生きているのに,なんで私がこんな辛い気持ちにならないといけないんだろう」と,ぼーっと考えたりもしてましたね。

フラッシュバックが起きて号泣するのは日常茶飯事,まともに授業を受けられず自己嫌悪に陥る…という辛い日々が続きました
正直,高校時代のカウンセリングはあまり助けになりませんでした。高1でのことは,たかが16~17歳の高校生が背負うには過重でしたし,それでもどうにか日常生活を送るために綻びや壊れかけた部分を修復しなければならなかったからだと思います。
以上が最も深刻だった,私の3回目の不登校経験です。まさに艱難辛苦,心理的に荒波どころではない騒ぎだった高校生時代に,どのように勉強して大学受験に臨んだかについては,改めて別記事にまとめたいと思います。
当事者の子どもたちをどう支えるか
教員って,学校に関して楽しい思い出が多かった人,もしくは登校することに違和感・抵抗感を感じた経験が少ない人が,相対的に多いんじゃないかなぁと推測しています。自然ななりゆきとして,学校に何かしらのトラウマを持つ人が,教員を志望するほどの強い動機を持つとは考えにくいからです。私の大学院時代や今までの教員生活を振り返ってみても,不登校を経験したことがあるという話は聞いたことがありません(もちろん,男性の先生が多数を占めるという特殊な環境にも起因していると思います)。
私自身身に染みて痛感しましたが,不登校になったきっかけや期間は本当に人それぞれです。中学・高校卒業まで続くケースや,ある日突然登校できるようになるケース,特定の教員の授業にだけ参加できる/できないケースなど,不登校状態への適応の仕方は子どもによって異なります。
ですので,学校へ行きづらく感じる子どもの保護者の方や担任の先生におかれては,どうかデータや一般論(正論)ではなく,その子自身(パーソナリティや得意なこと,やってみたいと思っていること,etc…)に目を向けて頂きたいな,と思います。
「どんな声かけをすればよいか分からない」というお声を耳にする機会も多々あります。これについて私が大事だと考える着眼点は
の3点です。その子の状況や現在の社会を考慮に入れ,客観的・理性的に感情に寄り添う視点が重要です。
上からの押しつけや感情論はNG!
ともすると忘れがちですが,保護者の方や教員と現在教育を受けている子どもたちとは,生きている時代がまるきり違います。最も分かりやすいのはコロナ前とコロナ以後の世界ですね。2025年の今でこそオンラインでの学習や出勤が当たり前の世の中ですが,2020年以前の「皆勤」を是とする雰囲気では通用しなかった/「甘え」とみなされていたと思います。逆も然りで,上の世代の常識が何年後かすると既に崩れていて,新たな常識に書き換えられたりもします。そのサイクルは年々早まってきている気もしています。
子どもを支える私たちも,そうした時代感覚を常に磨いていかなければと感じます。
おわりに:あなたの苦しみは,あなただけのもの
高校の頃通っていた心理士さんに「あなたはまだ恵まれている。世の中にはもっと辛い人たちもいますよ」と言われた時には,さすがに「この人に何が分かるんだよ」と心中で漏らし,号泣しました。
たしかに国ごとに福祉制度の違いがあるので,そこだけ見ればそう「見える」のかもしれません。ですが,人間というのは自分の苦しみの程度さえ鮮明に記憶したり,公平に比較したりすることができないものです。自分が「人生史上いちばん苦しかった」と感じる記憶は,常に上書きされていくのが摂理だからです。自分が苦しんだ経験についてでさえこんなふうにあやふやなのですから,況や他人の苦しみをや,というわけです。
ですから,なんらかの経路でこの記事にたどり着き,ここまで読んでくださったあなたへ。どうか,どうか自分を責めないでください。自分を傷つけないでください。
「不登校」というのは,教育制度を整備した人たちや研究する人たちが扱いやすいよう編成された「カテゴリー」にすぎず,それによってあなた自身が規定されることはありえません。
労働し,納税している大人でさえ生きづらく感じる今の世の中で,大人よりも感度が敏感な今の子どもたちが何の影響も被らないはずがありません。
毎日泣きじゃくっても良い。絶望しても良い。でも衝動的に自分を傷つけることはしないでほしい。「心地良いな」と感じる居場所を選ぶ権利は,あなたにあるのですから。
- 文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」2024年10月31日.(最終閲覧日:2025年9月6日) ↩︎
- 同上 ↩︎
- 同上 ↩︎
- MSDマニュアルプロフェッショナル版「抜毛症(トリコチロマニア)」2023年6月改訂.(最終閲覧日:2025年9月6日)
↩︎


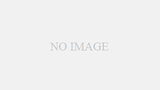

コメント