
ハーフのお子さんをお持ちの保護者の方も,必見です!
そもそもHSPとは?
HSPは「繊細で敏感な人」という一言に要言されます。元々は1996年にアメリカの臨床心理学者エレイン・アーロン博士が提唱し,現在国内でも心理学界隈で注目を集めているホットトピックです。日本に入ってきたのはコロナ禍前後。今でこそ「繊細さん」などのタイトルを冠する書籍がベストセラーコーナーに陳列する光景を頻繁に見かけますが,私が初めてHSPを知ったのも2020年でした。
また近年では,子どもに限定した「HSC(繊細な子ども,Highly Sensitive Child)」という呼び方も普及しつつあります。それだけ繊細な子どもについての理解と適切な支援が,保育・教育現場でも重要になってきていることが示唆されます。
HSPさんの特徴として「①感受性が豊かである ②五感のうち一つ,または複数の種類にまたがって敏感である(強度によっては,この性質によって不安感や緊張感が促進されやすい) ③他者の感情の機微を深く汲み取る ④一つの物事への探究心が強い」といったものが挙げられます。
アメリカに住むハーフやミックスのメンタルヘルスは深刻…
そんな特性を持つHSPですが,それではハーフであることとの関係性はあるのでしょうか。
残念ながら日本では個人ブログ以外,公的機関が公表しているエビデンスがなかなか見つかりませんでしたので,英語で文献を検索してみました。
例えば,他人種のバックグラウンドを持つ子どもや学生(multiracial young adults)の方がそうでない子ども・学生に比べ,メンタルヘルス上の課題が多く,精神疾患の発症率が高い傾向にあるという,米国国際社会精神医学会による調査報告が見られます。
さらに「米国不安とうつ病学会公式」ウェブサイトでも,言語・文化の多様性とメンタルヘルスに関わる記事が投稿されています。
「私は何であるか」と自己懐疑に陥り,インポスター症候群になる可能性が高まるとしつつ,
多民族コミュニティに属する人々にとって、一個人としての自立感と一致させつつ、アイデンティティの感覚と文化(への帰属感)との調和を上手く保つのは困難な場合が多く見られる。結果として、*置き換え(displacement)や自己不全感(inadequacy)、人種的曖昧さ(racial ambiguousness)が生じるのである。
ADAA Multiracial Communities
*置き換え(displacement)…心理学で,自分の欲求が満たされなかった時,それを補おうとして,欲求の対象や表現方法を別のものに置き換えようとする反応。イライラして物に当たることや,気分を満たすために過食・浪費をするといった行動が当てはまる。
としています。「自分は何(人)なの?」という疑問は,時として深刻な心理的ダメージに転化するおそれがあることが指摘されていることが分かります。
驚くべきことに,同記事では「アメリカでは精神疾患を抱える人のうち、4人に1人が2種類以上の人種的バックグラウンドを持っていると認識している」というデータが報告されており,
ある研究では、白人学生と比較して、混血/多民族の学生はメンタルヘルスが著しく悪化する確率が高く、保護要因も顕著に少ないことが示された。
ADAA Multiracial Communities
としています。アメリカでは「白人(White)」が対立項になることが多いのでピンと来ないかもしれませんが,要は日本で言うところの「日本人/それ以外」という構図と似たようなものです。
アメリカの調査結果ではありますが,「4人に1人」のミックスがメンタル上の健康に不安感を訴えているというこの数字,私たちも見過ごすことはできません。公にされていないだけで,同様の状況が日本においても発生していることは容易に推測できます。
強度のHSPハーフとして
私自身も幼少期から,音と匂い,人の感情に対して特に敏感でした。大きな物音や怒鳴り声を聞いて,その場から動けなくなったり,呼吸が浅くなったりしましたし,誰かが泣いている様子を見て自分も涙することも珍しくありませんでした。
HSPという用語を知り,なおかつ自分は強度HSPの傾向を持つと知ったのは大学2年生の時でしたが,それまでは周囲に適応できていない自分の感覚がおかしいんだと,ただ耐え忍ぶ日々でした。
同じくハーフの友人数人に話を聞いたところ,友人たちも何かしらの感覚に敏感で,他の人が抱かないような疑問・考えを持つようだと気づきました。日本以外の言語・文化的環境に育った経験があることとHSPとは無関係ではないのではないかと考えるにいたったのは,こうした体感もあってのことです。
結論【子ども・成人問わずハーフはHSPになりやすい】
ここまで挙げてきたアメリカでの複数の報告を踏まえると,傾向としてハーフ(ダブル)はHSP/HSCになりやすいと言えそうです。
特に日本の場合,他国と比較した時に,ハーフの人口が少ない(地域によってはほとんどいない)特性が未だ色濃いため,偏見やステレオタイプにさらされやすい側面があります。これは私が小学生だった10年以上前と比べても,そう思います。
ただし,メンタル疾患の複雑性や多様性がそのまま敏感さに繋がることに関するデータはまだまだ不十分であることもうかがえます。言うまでもなく,ひとくちに「日本で生活をおくるハーフ」と言っても,学校生活の中でのことか,社会人以降の会社の中でのことかといった「集団の多様性」,そしてその人自身の持つ「言語・文化的多様性」はさまざまです。
社会学・教育学が中心となって,この領域の研究がどのように進むのか,これからも注目したいと思います。
最後に…「英語」「白人」を至上とする社会に疑義を呈した英語の詩の一節を紹介させて頂きます。私のように,日本に住むハーフにとっても美しく勇敢な詩だと感じましたので,ぜひ全文も読んでみてください。
私の物語は*1あなた方のもの。
だからこそ今,私は私自身を統制する声を取り戻す。
私は「雑種」でも*2「ハーフカースト(half-caste)」でも「希少種」でもないのだから。
単純に、私は「全体」なのだ。
THE TALE OF ACCEPTANCE – A POEM BY LILY PEACH ELLIOT
*1「あなた方のもの」…原文中に「もはやイギリスの時代ではない(Britain is no longer great)」とあるため,おそらくイギリス社会全体を指すと思われる。
*2「ハーフカースト」…いわゆる「混血」。白人と,白人に征服された人種との間の子ども。
HSPハーフさん向け!お役立ちリソース
どうしても英語のウェブサイトが多くなってしまいますが,Google翻訳やDeepLなどで簡単に日本語訳できますので,ぜひ覗いてみてください。
Embrace Race – Resources for Mixed Race Children …ハーフ/ミックスの子どもたちへの支援や授業案などが豊富に掲載されているので,教育者や保護者の方々にとっても使いやすいと思います。
MIXEDLIFE …ミックスの方々によるアート作品が数多く公開されています。上記に引用した詩の一節も,こちらのサイトから見つけてきました。

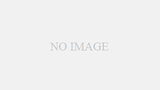
コメント